 |
平成19年度 神崎郡歴史民俗資料館講座録集 |
|
 ≪平成19年度連続講座≫ ≪平成19年度連続講座≫
| 開 催 日 |
講 座 名 |
講 師 |
場 所 |
時 間 |
| 第1回 |
5月26日(土) |
埋蔵文化財からみた福崎盆地 済
-盆地内の遺物からみた古代道路の想定- |
吉識雅仁氏
(兵庫県立考古博物館) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第2回 |
7月21日(土) |
郡役所が残るまち福崎 済 |
奥村 弘氏
(神戸大学 文学部教授) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第3回 |
9月9日(日) |
播磨国田原荘と地域の寺社 済 |
前田 徹氏
(兵庫県立歴史博物館) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第4回 |
11月18日(日) |
赤松氏の播磨支配について 済 |
小林基伸氏
(大手前大学 文学部准教授) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第5回 |
2月23日(土) |
近畿と北陸をめぐる<王の舞>の変容の考察済
-若狭・播磨・紀州の事例研究から見えてくるもの- |
大渡敏仁氏
(芸術文化学博士) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
 平成19年度「播磨の歴史・民俗行事を考える」講座録集 平成19年度「播磨の歴史・民俗行事を考える」講座録集
<第5回 講座録>
日 時:平成20年2月23日(土) 13時30分~15時
演 題:北陸と近畿をめぐる<王の舞>の変容の考察-若狭・播磨・紀州の事例研究から見えてくるもの-
講 師:大渡敏仁氏(芸術文化学博士)
2月23日、歴史民俗資料館にて第5回目の連続講座が開催されました。
今回は、資料館の講座でもお世話になっている大渡先生にお越しいただきました。
今回のテーマは、「北陸と近畿をめぐる<王の舞>の変容の考察」ということで、
近年、先生が研究されていた集大成ともなるべくものの内容でした。
<王の舞>とは、福崎町では浄舞として親しみのある民俗芸能です。
昨年の10月には、当町余田大歳神社浄舞保存会の皆さんが、兵庫県を代表して、
全国民俗芸能大会へも出演され、記憶に新しい功績でもあります。
本講座では、広域にわたる事例紹介をはじめ、行事は同じものであっても、
地域によってその形は異なり、民俗芸能のおもしろみを見つけることができたのでは
ないでしょうか。
福崎町の事例紹介では、練習風景が紹介されました。
民俗行事全般に通じることですが、行事はこのような練習や準備があってこその本番です。
この紹介からは、伝統芸能が継承されていく大切さを改めて感じることができたように思います。
本年度の講座は本講座を持ちまして終了しました。
ご講演いただきました先生方をはじめ、ご来館いただいたみなさん、
ありがとうございました。
また来年度も、このように講座を通して地域を見つめる時間をみなさんと過ごしたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いします。
<第4回 講座録>
日 時:平成19年11月18日(日) 13時30分~15時
演 題:赤松氏の播磨支配について
講 師:小林基伸氏(大手前大学 総合文化学部准教授)
11月18日、歴史民俗資料館にて第4回目の連続講座が開催されました。
今回は播磨激動の戦国時代に活躍する赤松氏とその支配についてのお話を、
講師として、大手前大学より小林先生にお越しいただきました。
今回の内容は、この歴史民俗資料館連続講座で「播磨の歴史・民俗や行事を考える」を
テーマとするなかでも、待望のお話ではなかったでしょうか。
動乱の戦国期、それは播磨においても同様であり、赤松氏をはじめとして
様々な思い、策略が交差し国内の勢力構図は入れ替わりの激しい時代でした。
この講座では、赤松氏を中心として当時の動きや実情、支配権力の移り変わりに
ついて大変くわしく教えていただきました。
1時間半の講演時間はあっという間にすぎ、まさに戦国時代の流れを駆け足で
追う充実した時間ではなかったでしょうか。
最後には近年行われた、赤松氏の拠点置塩城の調査報告から、
研究成果としての新しい見解についても紹介いただきました。
郷土でも関心の高い赤松氏。
今日の話を聞くと、ふとゆかりの地を眺めてみたとき、当時の動乱絵巻が思い浮かぶようです。
そして、少し身近にかんじることができるのではないでしょうか。
次回は本年度最後の講座です。
この講座で大変お世話になっている大渡先生にお越しいただきます。
また資料館でお会いしましょう。
<第3回 講座録>
日 時:平成19年9月9日(日) 13時30分~15時
演 題:播磨国田原荘と地域の寺社
講 師:前田 徹氏(兵庫県立歴史博物館 学芸員)
9月9日、歴史民俗資料館にて第3回目の連続講座が開催されました。
今回は郷土の中世のお話。講師として、兵庫県立歴史博物館より前田学芸員にお越しいただきました。
本講座では、限られた中世史料のなかから、当地域に現在も残るお寺や神社を中心とした、
田原荘園内の当時の様子や今日にいたる流れについて分かりやすくお話いただきました。
田原荘は、その荘域を示す史料が残っており、その範囲は現在の田原地区とほぼ同じです。
地区の中には、当時の史料に出てくる地名や寺社の名前などがそのまま残っているため、
私たちにもとても親しみのある内容でした。
また、当時の関連する石造物を紹介していただき、
なぜここに建てられたのかなど、その板碑に込められた背景をくわしく教えていただきました。
一つの文化財から、当地域と関係する人物とのつながりを見つけることができ、
より一層地域の文化財としての親しみや、そこに息づく歴史の流れを知ることができたのでは
ないでしょうか。
この講座を通して、また一つ郷土の歴史扉を開くことができました。
またみなさんと、次の扉を開いていきたいと思います。
次回は、播磨ゆかりの「赤松氏」のお話です!
<第2回 講座録~歴史民俗資料館25周年記念講演会~>
日 時:平成19年7月21日(土) 13時30分~15時
演 題:郡役所が残るまち福崎
講師:奥村 弘氏(神戸大学 文学部教授)
7月21日、歴史民俗資料館にて第2回目の連続講座が開催されました。
今回は、今年開館25周年を迎えた資料館の記念講演会として、
神戸大学より奥村先生にお越しいただき「郡役所が残るまち福崎」のお話いただきました。
いつも講座でお越しいただいている、この資料館の建物は
明治19年に建てられた当地方の郡役所でした。
そこで、今回はこの「郡役所」にスポットを当ててのお話です。
講演では、まず「郡」とはどういった地方自治の単位だったのか、
また、歴史的な「郡」の位置づけ等について、そして、県内の地方制度の成立過程や、
そこから生まれてくる「郡役所」の成立について
分かりやすくお話いただきました。
また、この神崎郡役所の当時の様子を思い起こさせるようなお話を、
関連の資料とともにご紹介いただきました。
「郡役所」としての姿を今は見ることができませんが、このような講座をとおして、
当時の様子を知ることにより、今ある資料館の中に息づく郡役所の姿を
思い描くことができたのではないでしょうか。
講演の最後には、地域歴史遺産としての郡役所についてもふれていただき、
この貴重な文化財を、これからも郷土の中で広く活用し、大切に守っていく
思いを刻むことができました。
次回は、中世のお話。
郷土の田原荘と寺社についてご紹介いただきます!
<第1回 講座録>
日 時:平成19年5月26日(土) 13時30分~15時
演 題:埋蔵文化財からみた福崎盆地
-盆地内の遺物からみた古代道路の想定-
講師:吉識 雅仁氏(兵庫県立考古博物館/福崎町文化財審議委員)
5月26日、歴史民俗資料館にて第1回目の連続講座が開催されました。
本年度は、様々な視点から郷土を見ていく講座が予定されていますが、
今回は、講座では初めての考古学という視点からのお話でした。
まずは、文化財全般そして埋蔵文化財とはどういったものなのかというところから、
文化財の分類、種類についてや、県内の特徴ある遺跡の紹介など教えていただきました。
そして、福崎盆地の地形や播磨の特産である石棺についてのお話がありました。
石棺については、町内でも数多く確認されています。
今回お話いただき、地域に残る文化財について、
改めて知るきっかけにもなったのではないでしょうか。
これらの点在する地域の文化財を結ぶことにより、地域の全体像がみえ、
全体像からは、当時の物流の流れなどが分かります。
そして、そこからみえてきたものは、当時の道でした。
これからも資料館では、地域の点を見つけ、講座をとおして
たくさんの点を結ぶことができればうれしく思います。
次回は、資料館の建物である「郡役所」についてのお話です!
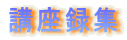
 平成18年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集 平成18年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集
 平成17年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集 平成17年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集
 平成16年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集 平成16年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集
◆問合せ先◆
神崎郡歴史民俗資料館
℡:0790-22-5699
※お問合せ・お申込みは資料館まで。 |
|
 |
|
|
